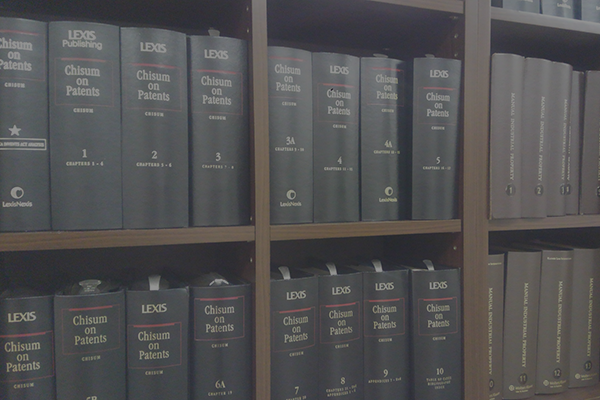NEWS
お知らせ・新着情報
- IPニュース
- ニュースレター第37号「日本における先使用権制度」
弁理士のご紹介
Patent Attorney
ますます複雑化し絡み合う分野。
それぞれの得意分野を持った弁理士が、
共同してお客様をサポートいたします。
私たちは、知的財産のトータルアドバイザーを目指します。
業務体制について
弊所は、業界に先駆けて在宅勤務での業務体制を整え運営しております。詳しくはこちら(「コロナ禍における業務への取り組みについて」)をご参照ください。